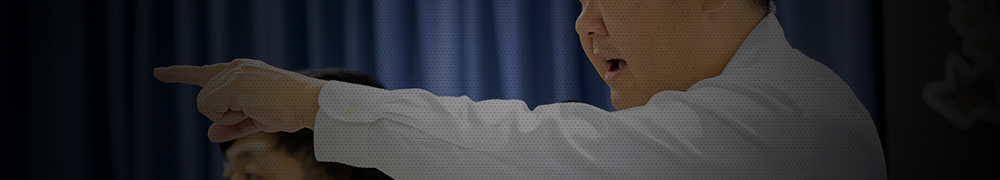
オークションのいろは
COLUMN
リユース経済新聞2025年6月25日発行号 掲載コラム『ブランド市場バイヤー 齋藤 清の俺に学べ!!』
第130回 揺れる市況と箱番号の心得
2025.6.254月から世界を賑わせている“トランプ関税”の影響が、じわじわと効いてきています。6月現在の相場は落ち着いているものの、全体としては低空飛行が続いています。北米向けの輸出は各社とも停止状態、海外のショーへの参加も見送る企業が増えています。国内の古物市場の状況を見ても、ロレックスのプラチナデイトナや200万円を超えるエルメスといった高額帯の商品も足が止まっています。
7月からは、アメリカ→EU向けの50%関税が追加される可能性があり、90日間の猶予が設けられていた各国向け関税の一時停止措置も、いよいよ期限切れを迎えます。このまま新たな局面に突入となれば、また相場が大きく動くかもしれません。買いも売りも、タイミングと読みが肝になります。
こんなときこそ、オークションへの出品にもひと工夫加えたいところ。今回は「箱番号」について、少し触れておきます。
落札価格を左右する箱番号 競り順にも工夫を
皆さんは、箱番号って気にされたことありますか?
オークションで競りに出される商品の並び順のことですが、かつては会場型の手競りでは、早い時間に競りにかけられたほうが高く売れやすいとされていました。競り始めは買い手も元気で、資金も温存している。逆に後半になると、バイヤーたちも疲れてくるし、競り合いの熱も落ち着いてしまう。実際、会主側もスタートダッシュを狙って、高額品や注目アイテムを若い箱番号に置く傾向がありました。
最近はオンラインや入札方式が主流になってきて、箱番号が落札価格に影響するケースは減ってきました。ただ、昔からオークションに参加している質屋系のバイヤーさんを中心に、「若い番号=良品が出やすい」という感覚は今も残っているようです。だからこそ、できれば若い番号を取りにいきたいところです。
でも、初出品で若い番号がもらえるかというと、そんなに甘くはありません。やはり常連になって信頼を積み重ねるのが近道です。あとは、出品する前に「今回これくらい出しますよ」と、あらかじめオークション主催者に伝えておくのも有効です。主催側も全体のバランスを見ながら箱番号を振っているので、事前に情報があると若い番号に回しやすくなります。逆に、締切ギリギリに出品物を送る方は、どうしても後ろの番号になりがちですね。
出品の際、オンラインや入札方式であれば、指値(希望落札価格)はさほど気にしなくても大丈夫です。ただし、あまりに相場からかけ離れた価格を付けてしまうと、進行が止まってしまうことも。その場合は、主催側からも「この値付けだと厳しいかも」と助言が入ることもありますので、事前のコミュニケーションが、お互いにとってプラスになります。
相場が不安定な今だからこそ、情報収集はいつも以上に大事です。オークション落札相場の検索サービスなど、カテゴリ別に相場の動きが一目で見られる便利なサービスは、普段以上に注視していきましょう。
また、こうした状況下では、各オークション主催者側もさまざまなサービスの見直しが図られていくことでしょう。ちなみに当会でも、従来の開催に加えて月末にも新たな会期を設けるなど、市場の変化に対応した取り組みを進めています。売り手、買い手、両方のニーズに応えられるような場づくりを目指して、こちらも日々アップデート中です。
先行きが読めない時代ではありますが、だからこそ面白いのがこの仕事。相場の波にうまく乗っていきましょう。
